2018年01月09日
七草がゆ

1月7日は七草がゆを頂く日。
あちこち駆けずり回ったが七草がなかなか手に入らず、大分駅構内でやっと手に入れたくまモン七草。
産地は南小国とのこと。
がんばろう、熊本!
南小国と言えば、久しぶりに「林檎の樹」にアップルパイを食べに行きたいな。
学生時代にはよく訪れたものです。
http://www.ringonoki.co.jp/ringonoki/
2017年12月20日
内閣府調査、こどもと若者白書
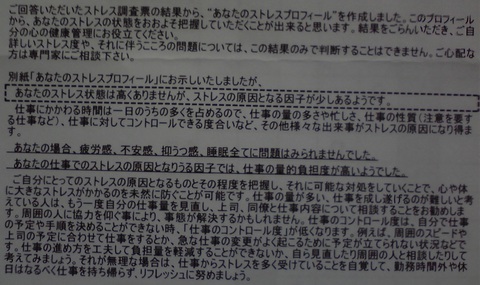
職場から、ストレスチェックテストの結果が返ってきた。
「あなたのストレス状態は高くありませんが、ストレスの原因となる因子が少しあるようです」
「あなたの場合、疲労感、不安感、抑うつ感、睡眠全てに問題は見られませんでした」
「あなたの仕事でのストレスの原因となりうる因子では、仕事の量的負担度が高いようでした」
とのこと。
これを見て、以下の話を思い出した。
職場は、自分の居場所として安心して過ごせる場所としては、最下位だった。
ほかの場所に比べると確かに安心して過ごせないと思うけど、当たり前と言えば当たり前。
若い人たちにとって、地域社会や学校よりもサイバー空間の方が居場所があると思える、というのは、ちょっと深刻な気がする。
<高校生から始める現代英語、2017年11月23日放送分から>
2016年末に行われた調査に基づく、内閣府によるこども・若者白書最新版より。
15歳から29歳までの男女6000人が対象。
以下に示すもののうち、どこにいるときなら自分の居場所として安心して過ごせるか、という質問。
・自分の部屋:89.0%
・自分の家:79.9%
・サイバー空間:62.1%
・住んでいる地域社会:58.5%
・学校:49.2%
・職場:39.2%
これら6つの環境を全てを安心できるとした人の約90%は、今の生活に満足していると答えた。
これら6つの環境はすべて安心できないとした人のうち、今の生活に満足していると答えたのは25.3%に留まった。
2017年12月10日
近頃のシャーペン

社会人になってから、シャーペンを使う機会はめっきり減った。
鉛筆はときどき使うのだが、シャーペンは使わない。
だいたい、消えてしまう筆記具を使うことはあまりない。
近所のスーパーが10%offの日だということで、大量買出しの荷物運び要員として駆り出された。
ようやくお買い物が終わり、そろそろ帰ろうかというところ。
子供から電話がかかり、
「シャーペンの芯を買ってきて」
とのこと。
うちの子供たちは、毎月の小遣いを受け取ると、キチガイのようにシャーペンを買いに行く。
筆箱の中はシャーペンで溢れている。
最近のシャーペンにはいろいろと新機構が組み入れられているらしい。
芯が折れないとか、いつも先がとがっているとか。
そのためか、芯も細くなる傾向にある。
かつては0.5mmだけだったように思うが、最近は0.3mmとか、0.2mmとか、0.7mmとかあるらしい。
ハイテクなんだかローテクなんだか、よくわからない。
でも、いつも使う道具にはこだわりたい、という彼らの気持ちだけは、よくわかる。
2017年12月09日
Oh, my goodness!

僕らの世代では、英語で「なんてこった」というときの定型表現は、
”Oh, my god!"
だったり、
"Jesus christ!"
だったりした。
最近のNHKラジオ英会話を聞いていると、ケンさんやケイティーさんがことあるごとに
"Oh. my goodness!"
"Goodness!"
とつぶやいている。
GoodnessはGodの婉曲表現とのこと。
宗教の多様性に配慮して、自然とこんな形になったのかもしれない。
留学生についても、"foreign student"ではなくて"international student"と呼ぶのが主流なのだとか。
まだはっきりとは取り扱われていないものの、LGBTに配慮して、どのような主語を文脈の中で用いるかも、注意する必要がありそう。
2017年12月08日
伝説の叔父

わが一族では、伝説的に語られる叔父。
ミカン箱を机に勉強し、かんなわから旧制第五高等学校を経て、東京帝国大学の法学部に入学した。
外交官を目指していたそうだ。
そして、入学から1週間ほどして、召集令状が彼のもとに届いた。
一族はみな、同じ墓所に入っているが、この叔父だけは別の墓石をしつらえられて、祭られている。
ただし、その墓所に遺骨は収められていない。
第二次世界大戦後シベリアに抑留され、その後北朝鮮で病死し、故国に帰ることができなかったと聞き及んでいる。
はかなくも、叔父の夢は異国の地に散り果ててしまった。
叔父の苦しみを少しでも理解しようと、この夏の命日にお参りする前に、山崎豊子の「不毛地帯」を読んだ。
シベリア抑留は、想像を絶する過酷な環境だった。
怜悧なたたずまいのこの叔父は、どのような辛酸をなめたのか。
私が2歳のころに亡くなった祖父は、私をそれはそれはかわいがってくれたという。
私の叔母は、この叔父の遺志を是非私に継いでほしいと、ことあるごとに語っていた。
残念ながら私は全く違う道に進んでしまったけれど、叔父が生きていたら、今のこの世界をどのように見つめるだろうか。
2017年12月03日
都道府県と県庁所在地
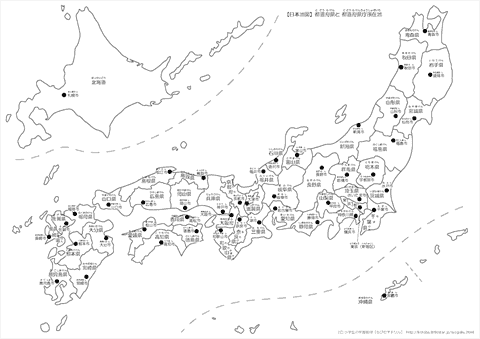
子供の勉強に付き合っていると、ときに世の無常を思い知る。
中でも、県庁所在地が変わったことにはたまげる。
なにを隠そう、私は県庁所在地を覚えるのが大の苦手だった。
小学校3年生か4年生のころ。
社会の授業で、県庁所在地の小テストが繰り返し行われたことがある。
今でもあのときの屈辱は忘れない。
1回目は30点。
2回目は40点。
見かねた母親が、3回目のテストの前の夜、つきっきりで繰り返し一問一答に付き合ってくれた。
最後の3回目は100点。
だから、臥薪嘗胆ののちの成功体験としても思い出深い。
そんなわけで、小学生時分に覚えた都道府県と県庁所在地の知識は、今でも頭にこびりついている。
私も、名実ともにおっさんになった。
地図上の土地に実際に行って、珍しいものを見て、おいしいものを食べて、体験とともに知識は四次元的に広がっている。
だから、いまごろになって県庁所在地がかわったと言われても困るのだ。
日本のはるか南にはオーストラリアがあるように、県庁所在地というのは未来永劫変わらないものと思っていた。
埼玉県の県庁所在地は「さいたま市」?
「浦和市」に決まってんじゃん!
長野県の県庁所在地は「長野市」?
「松本市」って書かないと、100点取れないよ!
・・・というのは、昭和生まれの言い訳らしい。
子供の教育は、子供のためならず。
自分の知識の更新の機会と捉えた方がいい。



